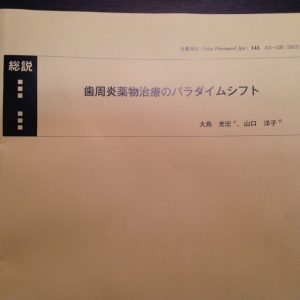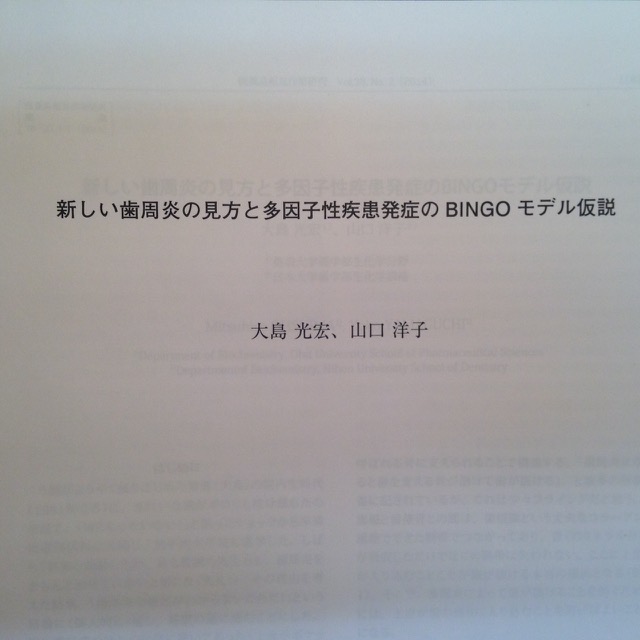先週、ビジネスジャーナルという情報発信サイトの連載に寄稿した歯周炎に関するものに、多少の加筆、修正したものをこのブログに載せました。
そしてその寄稿文が編集されビジネスジャーナルに掲載されるのを待っていましたが、ビジネスジャーナルから内容が専門的過ぎて分かりづらく、このままでは掲載できないとのことでした。
読み返してみると、やはり一般の方には分かりづらいと判断されるのも仕方ないと思えましたので、再度書き換えて投稿しようと思います。
今回の歯周炎に関する投稿は、どうしても歯科医が多く読むであろうブログ村を意識したこともあって内容が専門的な方向へ傾いたのは否めないところです。
しかし、先週書いた歯周炎のブログの内容は歯科医の方達にはどう捉えられているのでしょうか?
私がこの歯周炎関連繊維芽細胞を知った時には大きな衝撃を受け、普段の臨床で歯周病に感じていた違和感や漠然としていた捉え方へ、はっきりとした道筋を感じたのですが。
炎症を伴わない歯肉退縮などの歯周組織破壊を日常の臨床上目にしていると思うのです。
例えば、乳歯から永久歯への萌え替わりの時に、乳歯の歯根吸収や乳歯の歯周組織の破壊が起こっている場面、また第一、第二大臼歯、親知らずなど萌え替わりではなく、新たに歯肉を破って萌出する場面では、細菌性の炎症によらない歯周組織の破壊が起こっています。
いわゆるアポトーシスのくくりでしょうか。
実際、親知らずなどが萌出し始めている時のその現場に、歯周炎関連繊維芽細胞が発現していたりすると面白いのですが、歯周炎が完全にコントロール出来るようになることは、患者さんにも歯科界にとってもこれ以上ない福音です。
再三の紹介ですが、総説(日本語)「歯周炎薬物治療のパラダイムシフト」大島光宏先生、山口洋子先生著。 是非、ご一読下さい。
林歯科・
https://www.exajp.com/hayashi/
![]()
↑↑歯科医療情報ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックをお願いします。