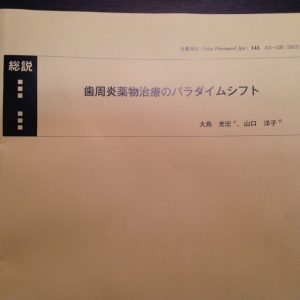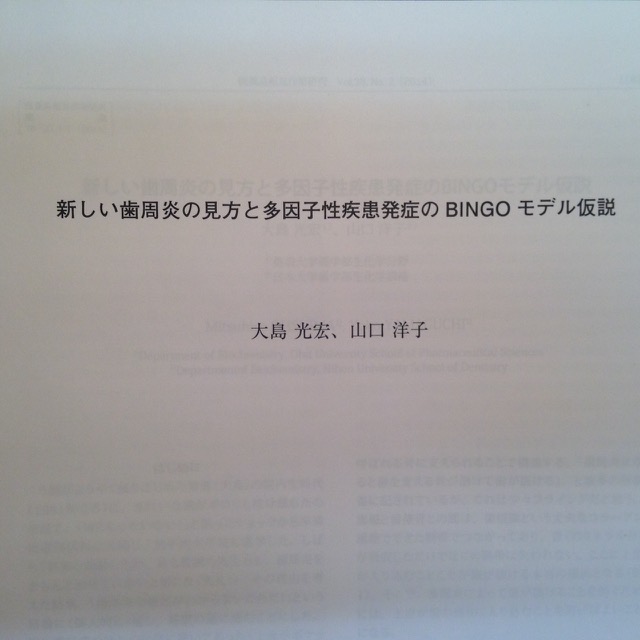去る6月15日(水)ホテルニューオータニ、翠鳳の間で催されたロータリークラブでの講演内容です。

目からウロコの歯の話、なぜかみ合わせは大事なのか?
講演者 林歯科/ 院長 林 晋哉先生
口とは何か、両手で三角形を作り、顔に当てると口と鼻がすっぽり入ります。命の循環は入れて出す、その入り口がこの三角の中に集中しているのです。命の源である口に不調があると全身に影響します。その口の健康に大きく影響するのが「噛み合わせ」です。
口は食べる、しゃべるだけではなく、噛みつく、物を保持する、愛情表現をするなどがあります。口のなかでも歯は特殊な器官であり、唯一外に出た骨です。
口がうまく機能するということは、軽やかに働くということです。
口を動かす時、誰も考えて動かしていません。なぜなら口をスムーズに働かすための咀嚼システムがあるからです。言語、歩行のシステムと似ています。歯が生えてきて、触れ合うことでこの場所に歯があるという情報が毎日脳に入っていき、脳が統御していきます。歯が一本不調になると、システムが変化していきます。
その変化が許容を越えると、システムに混乱を起こしていろんな悪影響が出てきます。システムを良好に維持するためには、システムが拠り所にしている歯から脳への入力を平均的にちゃんと入るようにしておくこと、つまり噛み合わせを正しく整えておくことが大事なのです。
片噛みを続けていると片側の筋肉が発達して顎の骨が縮小します。
これは、機能から形態が引っ張られていることです。人体構造として2本足で立つことはすごく不合理で、重い頭部を支えるために首回りに強靭な筋力が必要です。この強靭な筋肉のバランスに強く影響を与える器官が口なのです。また、人間の祖先は猿と言われ、その祖先は魚と言われています。
この時代から魚の口の周りに大事なものが全てありました。この筋肉がどこに発達していったかというと、呼吸筋で、現代の人間の体全体に分布しています。口に不調和があると、全身に対して影響してもおかしくないということです。
歯科治療を一言でいうと顎口腔系へのストレスの軽減です。
ストレス因子は、咬合状態(噛み合わせ)、顎関節の状態、症状のある歯や部位の存在などがあり、特に重要なのは食いしばり、噛みしめです。しかし、なかなか歯科の世界で噛みしめ対策をするというのは広まっていません。噛みしめ対策の根本的な意味合いは、脳の中にできている噛みしめるという強い癖を取っていくことです。
単純にマウスピースをすることではありません。マウスピースも一番大事なのは噛み合わせがどこで噛みしめても安定できるように調整されているかどうかです。体の健康は口の健康が支える、口の健康は良い咀嚼システムが支える、良い咀嚼システムは正しい噛み合わせが支えているのです。
歯科医療は、成長期とそれ以降とでは明確な治療目的の区別が必要です。
成長期は正しい咀嚼システムと顎口腔系の育成と成熟で、それ以降は顎口腔系のストレスの総量を軽減していくことです。歯科治療の目的は無意識に両方で噛める状況を(入れ歯でもインプラントでも)きちんと回復し維持し、口を意識しないで社会生活を送れるようにすることです。口を軽く考えず、大事にすることこそが長く健康寿命を保つ近道です。
林歯科・
https://www.exajp.com/hayashi/
![]()
↑↑歯科医療情報ブログ・ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックをお願いします。